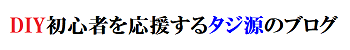以前から気になっていたお風呂の排水口(排水溝)のカバーをDIYで製作することにしました。
理由は現在のカバーというか蓋は金属製で重い上にメッキが剥がれてあちこち錆びてきているからです。
サビだらけの排水口カバー
こちらはカバーを外した状態です。
掃除したばかりなのできれいですがいつもは髪の毛などが結構たまっています。

排水口のカバーを付けたところです。
あちこち錆びだらけ

もともとメッキがされていたのが部分的にメッキが剥がれてそこからサビが出てしまったようです。
更にこのカバーの欠点は硬く重い!
鉄なので重くて当然なのですが、掃除する為に外したりする時にあちこちに当たったりして浴室を傷つけてしまう恐れがあるのです。

裏側は更にサビがひどいです。

側面は一部サビが落ちて欠けている箇所があります。

排水口のカバーのDIY
初めは同じカバーを購入しようと思いカタログで探したのですが、何しろ20年以上前に建てた家なので同じカバーはもちろん、ここにハマる他のカバーも見つけられませんでした。
それなら自分で作ってしまおうと考えたわけです。
DIYerですから・・・
さて、自作するカバーに使う材料がこちら。
以前に使用したヒノキ材の残りです。
板厚は現在の鉄製カバーと同じ6mmで幅は24mmです。

現在のカバーは一辺が163mmの正方形なので139mmの長さに4本切り出して、中の入れる3本は115mmです。
これを接着剤だけで固定するので両端の直角がキチンと出ていないとしっかりくっつかないので小口をカンナで仕上げ

そしてボンドで接着
写真に写っていませんが、ボンドが乾くまで旗ガネやクランプでしっかり固定しました。
後で思ったのですが、外周の板は全部同じ長さにしないで、左右を長く上下の板は左右の板に挟み込むように短くした方が良かったと思いました。
理由はその方がクランプがやりやすいからです。
今回この作り方にしたためクランプが結構大変でした。

ワトコオイルで塗装
ヒノキは檜風呂に使われるくらいだから水には強い方ですが、お風呂場は水がかかっている事が多いので、ワトコオイルで保護することにしました。
よく使うワトコオイルはミディアムウォルナットやダークウォルナット色ですが、今回はホワイト色にしました。

ヒノキ製の排水口カバーの完成です。
今まではお風呂に入っている時サビだらけの排水口は見たくなかったのですが、このカバーに代えてからお風呂場の中で唯一の木材であるこの排水口カバーをチョコチョコ見るようになりました。
お風呂に入っている時も木を見るとなんか落ち着きますね。

排水口カバーの補修
(6月25日更新)
排水口カバーが2日ほどでボンドがとれてしまったので補修しました。
やはりイモ接ぎでボンドだけでは弱かったか・・・

対策としてダボで接ぐ事にしました。
しかし厚さ6mmの板に使うダボなんてあるんでしょうか?
あるんです!
それはどこの家にもある「爪楊枝(つまようじ)です。

2.5mmのドリルで穴をあけるとちょうど良かったです。
ある程度入れたら出っ張りを10mmくらい残してカットします。

こんなに細いダボマーカーは無いので、爪楊枝の先にマジックを塗ってそれが乾かないうちに相手側に押し付けてマーキングします。
見えにくいと思いますが、指先で指している所にマーキングの跡が見えます。

こんな感じで爪楊枝ダボを使い再度接着し補修が完了しました。
これからこのワトコオイルで保護したヒノキがどれくらい持つのか、どれくらい経つとカビが生えてくるのか観察して行きたいと思います。

(2019年10月28日更新)
塗装をウレタンニスに変更
ワトコオイルではやはり常時水に濡れる箇所には厳しかったようです。
一度サンドペーパーで擦って地肌を出して再塗装です。

今回はスプレー式のウレタンニスで塗膜を作ることにしました。

3回スプレーを重ねました。
1回スプレーしてから再度スプレーするまでに2時間ほど置きました。
また、最後の仕上げスプレーの前には、#350のサンドペーパーで軽く塗装面を磨き表面のデコボコを取り除きました。

3回ウレタンニスを重ねたので結構強固な塗膜ができたと思います。
最後までお読みいただきましてありがとうございます!